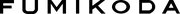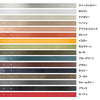ワイングラスの持ち方「ステムを持つのは間違い」という説は本当?:仕事も人生も豊かにするワイン社交術vol.01
ワインはビジネスにおけるコミュニケーションを円滑にし、プライベートでも私たちの生活を豊かにしてくれます。本連載では、ワインライフを楽しむための知識を、初心者にも分かりやすく解説いたします。今回は、連載開始を記念して、レコール・デュ・ヴァン創立者・校長の梅田悦生さんからご寄稿いただきました。
お酒を飲む時には、盃にもこだわりたいものです。ワインにはワイングラスですね。なんと、古代ローマ時代に、すでにガラスで出来たワイングラスがあったとか。ガラスの歴史は紀元前4000年にさかのぼることができるとされていますので、決して不思議な話ではありません。
古代ローマの頃からワイングラスには本体(ボウル)、脚(ステム)、台(プレート)があったはずです。シルクロードを旅して我が国に来た正倉院の宝物のひとつ「コバルト・ブルーのワイングラス紺瑠璃杯」は、そのルーツを紀元2世紀頃に求めることができますが、そのコバルト・ブルーもこのスタイルです。
マナーを知れば、ディナーがさらに楽しくなる
今日は親しい友人のお嬢さんの就職祝いのディナーで、テーブル・マナーを教えてやってほしいという友人の頼みで私が来た、というシチュエーションで、ワインマナーの基礎について解説します。
あっ、予約の時刻が近づいてきました。そろそろ、レストランに行きましょう。美しくセッティングされたテーブルにつきました。磨き上げられた銀食器、見事な装飾がほどこされたお皿、形の異なるワイングラスが5脚もあります。シャンパーニュ用が1脚、白ワイン用が1脚、赤ワイン用が1脚、デザートワイン用が1脚、最後の少し大振りなものはお水用です。
ソムリエがこちらに向かって来ました。うやうやしくシャンパーニュを持っています。あれはとても有名なシャンパーニュ、ベル・エポック。あのボトルにかかれた白いアネモネの絵は、エミール・ガレの作品です。
今日はあなたのお祝いですから、あなたが主賓ですよ。お店にはそのように伝えてありますから、にこやかに堂々と振る舞っていてください。
まず始めに、あなたのグラスにワインが注がれますから、テイスティングはお任せします。難しくはありませんから心配しないで。ソムリエが「お味見をお願いします」と言いますが、ワインが注がれている時にグラスを持ってはいけません。手はお膝の上、ベル・エポックが注がれているのを、にこやかにほほ笑みながら見ていましょう。
お味見ですから、グラスには少ししかシャンパーニュを入れてくれませんが、それでいいのです。ソムリエがボトルを持って、あなたのご判断を仰いでいます。では、グラスのステム持ってください。親指と三本の指でステムを挟んで持ちます。小指を立ててはいけません。
グラスをほんの少し傾けると細やかな泡がつながって糸のように見えるでしょう。グラスは高く持ち上げなくてもいいですよ。目の高さまで持ち上げるのは専門家の振る舞いです。お客様は自然で構いません。色を見ている振りをしましょう(笑)
グラスを鼻に近づけて香りをかいでごらんなさい。ちなみに、ワインでは臭いといわないで「香り」といいます。アカシア、サンザシ、白い花、グレープフルーツ、ライム、バニラの香りがするはずです。でも、今は考えなくていいですよ。何かわからないけれどいい匂いでしょう。少し飲んでください。口にふくむと言います。
おいしい? それは良かった。では、ソムリエの目を見て微笑んで「結構です」といってあげてください。白ワインも赤ワインも基本は同じですからね。

では、乾杯しましょう。今日はおめでとうございます。乾杯はグラスを持って、お相手と目を合わせて軽く頭を下げます。うなずく感じです。グラスをカチンと合わせてはいけません。上等のワイングラスはとても繊細に作られていますので、カチンと合わせるとヒビが入ってしまいます。大切な場で、グラスを傷つけては台無しです。
ワインが少なくなっても、自分で入れてはいけませんよ。また、テーブルでは女性のお客様はボトルを持たないことが原則です。グラスが空になったらソムリエを呼びましょう。ですが、プロのソムリエは、グラスが空になるまで気が付かないことはありません。
ワイングラスはステムとボウル、どちらを持つべき?
そうそう、グラスの持ち方については、いろいろな意見があるのですが、いまお教えしたように、ステムを持つのが「基本」です。テイスティングでは、ボウルのところを持つと、ワインの評価に大切な「ワインの色」と「ワインの粘張性」が見辛くなります。また、ボウルを持ち続けていると、ワインが温まってしまいます。大した温度の差が出ないという意見は確かにありますが、基本的な考え方です。
では、せっかくの機会ですから、ボウルを持つのが正しいといわれていることについても説明しておきますね。
国際的なマナーのことをプロトコールといいます。そのプロトコールに正式に書かれたものを拝見したことはありませんが、国賓を歓迎する公式の晩餐会では、ボウルを持つようです。英国の女王様が主催されてスペイン国王がお招きを受けた晩餐会の様子をインターネットで拝見することができます。なんと、お二方共にボウルをお持ちになっています。
「う…ん、そうするとテイスティングができないな」と思いましたか? 素晴らしい。あなたは素晴らしい。そのとおりです。ボウルを持つとテイスティングが十分にできません。では、なぜこのような違いがあるのかの説明をしましょう。
実は、公式の晩餐会ではテイスティングは誰もしません。晩餐会に出されるワインはすべて、あらかじめ会場に運び込まれる前に専門家によってテイスティングがなされていて、お客様に悪いものをお出しするはずがないのです。また、招かれたお客様がホストの出してくださった飲み物をテイスティング(味見)するなどとは、とんでもないことなのです。
宮中晩さん会に参加した方から伺ったお話の又聞きですが、「ワインの名前が何であるかはメニューに書かれていましたが、どなたもテイスティングはしておられませんでした。ワインが注がれる時にラベルを拝見するなど、とんでもないことでして、結局造り手は分かりませんでした(笑)」とのことだったようです。
晩餐会ではお料理もワインもほめてはいけません。美味しいのは当たり前なのです。ワインをほめるなどとは、畏れ多いことなのです。そうなのです、公式晩さん会ではテイスティングはありません。となると、ステムを持ってもボウルを持ってもどちらでもよいように思えます。とはいえ、ボウルを持つことに積極的な理由が何かあるかもしれません。
先にお話しした英国女王様主催の晩さん会の写真をよく見ると、女王様は手袋をしておられました。また乾杯用のグラスはステムがとても短くて、指が二本しか入らないようでした。
公式晩さん会の写真をいろいろ見ると、ステムに指が少しかかった形でボウルを持っている写真が一番多いようでした。しっかり保持することが最優先なのですね。それならばボウルを持ち方がより確実です。
国宝級とはいわないまでも、最高レベルの芸術的なワイングラスにはステムがとても細く作られているものもあります。そのようなグラスにワインを入れてスワリング(グラスを回すこと)などしては、ステムがポキンとゆきかねません。そのようなことになっては一大事ですね。

これらの約束事を知ったうえで、私たちはレストランでワイングラスのステムを持ってテイスティングしましょう。ボウルを持つよりもステムを持つ方がエレガントに見えるのは私だけでしょうか。テイスティングの時にはグラスを回しますが、ボウルを持つよりもステムを持つ方が回しやすいですね。ワインの色を見て、香りを楽しみ、味わいについて「美味しいですね」、と言葉を交わせるのは、楽しいではありませんか。
梅田悦生さんプロフィール
レコール・デュ・ヴァン創立者・校長。日本ソムリエ協会公認ソムリエ。赤坂山王クリニック院長。医師、医学博士、日本抗加齢医学会 専門医。フランス滞在経験5年、フランス・ドイツ・イタリアなど欧州ワイナリー訪問経験延150回以上。若き日にはフランスで、レジデント医師として5年に及ぶ臨床に携わった経験を持つ。主婦と生活社主催「アイデア料理コンテスト」ではサラダ部門でグランプリを受賞した。
ボルドーワイン、ブルゴーニュワイン、シャンパーニュワイン、アルザスワインの騎士ワインスクール校長としての経験は25年と大ベテラン。1992年から2002年までの10年間は、アカデミー・デュ・ヴァン校長としてスクールの発展に貢献し、受験の神様と呼ばれる。
著書:『ソムリエ初級講座』『ソムリエ試験受験対策実戦講座』などワインに関連するもの以外にも「新型インフルエンザ」「めまい」など医学に関連するものを合わせて著書は90冊を超える。
◆これからワインを知りたい方、ワインを学ぶ楽しさにふれるチャンス! ワインテイスティングを体験してみましょう。
「レコール・デュ・ヴァン1DAY テイスティングセミナー無料体験」